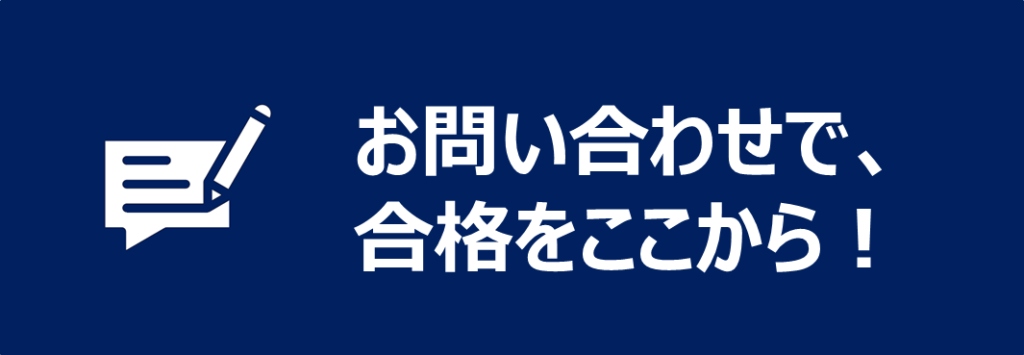【合格体験記】もう一度、自分を信じて──東大理三 合格
伊藤さん(仮名)|都内中高一貫校出身|2024年10月入塾
■ 理一から理三へ。迷いの先に見つけた、新たな進路
高校時代は高1から鉄緑会に通っていましたが、本格的に勉強を始めたのは高2でした。高3で成績が伸び、現役で早大理工と東大理一に合格しました。
しかし、東大に進学後、将来について深く考える中で、「このままの道でいいのか」と疑問が生まれ、公認会計士などの資格も検討しましたが、専門性を持ち、人の役に立つ仕事に就きたいという気持ちから、医師という道を真剣に志すようになりました。
最初は千葉大や科学大などの首都圏の医学部を考えていましたが、再受験の勉強を始めて約1ヶ月後の東大模試で理科三類A判定が出ました。
「この勉強量で行けるなら、理三を目指すべきだ」──そう確信し、目標は東京大学理科三類に定まりました。
■ 成績の波、そして不安。乗り越えるきっかけとなった出会い
東大模試は全部で10回受験しました。最初の頃はA判定でしたが、秋の東進模試以降、B判定に下がり始め、現役生の追い上げを感じ始めていました。
勉強を始めて3ヶ月が経った夏、既にピークに達していたような感覚があり、「このまま本当に伸びていくのか」と疑念が生まれました。理三を受けるべきかすら迷いがありました。
そんな時、はじめて人の意見を真剣に聞こうと決めて、当時メタスキリングで実施されていた無料面談を受けたことが、転機となりました。英語の点数が思うように取れず不安だった私に対し、英作文の時間配分の改善や数学の答案の書き方など、解像度が高く、かつ実践的なアドバイスをもらえました。「自分のやり方を見直そう」と思えるきっかけになりました。
■ 自分と向き合い続けた、日々の積み重ね
勉強時間は、バイトがある日は6〜7時間、ない日は9時間ほど。ほとんど家で勉強していました。勉強の誘惑となるスマホはタイムロッキングコンテナに入れ、半日以上使わないようにしていました。また、勉強中の眠気に対しては、集中力が切れたらコーヒーを一気飲みしたり、アイマスクをして10分だけ昼寝をしてリフレッシュしていました。
日々の問題演習では、すでに基本的なことはある程度固まっていたため、数多くの初見問題に触れて、応用範囲を広げていくことが重要だと考えたので、「同じ問題を繰り返さず、なるべく違う設定や出典の問題を使う」ことを心がけました。
解けなかった問題は「なぜ解けなかったのか」「何が足りなかったのか」を徹底的に分析し、そのすべてを一冊のノートに情報を一元化しました。
そのノートさえあれば、自分の課題と改善すべき点、習得すべき技術がすべてわかるようにしておき、入試本番でもお守りがわりに持っていき、メンタルの安定にも役立ちました。
■ モチベーションが下がった時期と、その乗り越え方
秋には、1週間ほどモチベーションが下がってしまい、勉強時間も4時間程度に減ってしまいました。理三を受けること自体にすら、迷いが生じていました。
ただ、その時に「自分は勉強に飽きているのでは」と気づき、それまで続けていた二次試験対策から、共通テスト対策に切り替えたことで、気分がリセットされ、再び前向きに勉強に向かえるようになりました。
■ メタスキリングとの出会い: 戦略的なアドバイス
再受験の秋、東大模試の結果が思わしくなく、自分の勉強法に疑問を持ち始めました。
特に英語で思ったように点数が取れず、「本当にこのやり方で合っているのか」と不安が募っていた時期。
そんな中で出会ったのがメタスキリングでした。
「最近の入試で東大理三に合格した人の話を聞いてみよう」――
そう思ってLINEで無料面談を申し込みました。
実際の面談では、英作文に時間をかけすぎている点や、数学の試験戦略など、東大入試で点を取るために必要な課題について、的確に指摘されました。
「これは参考になる」
直感的にそう感じ、その日からメタスキリングを本格的に活用するようになりました。
■ 日々の勉強報告によって消えた迷い
メタスキリングでは、日々の学習内容をSlackで報告します。
自分では意識しているつもりでも、気づかないうちに教科のバランスが偏っていたり、学習時間にムラが出たりすることがあります。
得意・不得意の偏りが少ない自分にとっても、第三者の視点から指摘をもらえることで、常に軌道修正しながら進むことができました。
進捗の管理や、ちょっとした疑問へのレスポンスもすぐにもらえる環境が整っていて、
迷いがちな再受験生活において、「自分は正しい方向に進んでいる」という精神的な支えにもなってくれました。
■ 実戦的な戦略と、点につながるアドバイス
メタスキリングの特長は、単なる「勉強法のアドバイス」だけではなく、「試験でどう得点を取りにいくか」という視点が徹底されているところです。
たとえば数学では、試験の最初の30分で各問題に5分ずつ目を通し、取るべき問題の優先順位を立てるという解き方を教えてもらいました。
実際の東大入試本番では、「1→3→6」の順番で解くという戦略を採用し、取り切るべき問題を確実に取ることができました。
加えて、東大模試の数学の問題に対して「別解」まで提示してくれるようなやりとりもあり、ただの答え合わせではなく、考え方の幅や柔軟性を身につけることができました。
■ 情報の質とスピードが違う。「合格までの時間を短縮できる」環境
再受験という限られた時間の中で、重要なことは「無駄な遠回りをしないこと」だと感じていました。
メタスキリングでは、学習計画を一日単位で具体的に落とし込み、常に自分の現在地と目標との差を意識しながら取り組むことができました。
たとえば、秋に英語の得点が下がっていたときは、「セット演習に切り替える」「英作の時間配分を変える」など、状況に応じた戦術的な修正がすぐに入りました。
これにより、「自分は今、何をすればよいのか」が常に明確になっていて、余計な迷いや焦りに飲まれることなく、勉強に集中することができました。
■ 「一人で考えすぎない」からこそ、最後まで折れなかった
一人での自宅浪人という環境の中、どこかで方針を間違えていたら、たった数ヶ月のブランクが命取りになっていたかもしれません。
でも、メタスキリングのコーチングや進捗管理のサポートがあったことで、学習の方向性を常にチェックしてもらいながら、ブレずに進み続けることができました。
精神的にも、「このやり方でいい」と信じられる環境は、再受験生にとって本当に大きな意味があり、そうした意味でも役に立ったと感じています。
■ 後輩へのメッセージ:「他人は関係ない。自分だけを見てほしい」
受験生へのアドバイスは一つです。
他人のことは見なくていい。自分だけを見てください。
SNS、特にTwitterなどでは、信じられないほど頭の良い人の情報が溢れています。
でも、それは99%の人にとっては役に立ちません。自分のことに集中し、今の自分に必要なことだけを見極めてください。
自分ができていない教科は何なのか。なぜできないのか。
それを一番わかっているのは、他の誰でもなく自分自身です。
徹底して自己分析をし、弱点と向き合ってください。
人と比べるのではなく、自分に目を向けること。
それが、合格への一番の近道です。
まずはお気軽にご相談ください!
初回60分間の入会面談を完全無料で承っております。
あなたの学習目標を最短ルートで達成するために、時間管理の技術、モチベーションの維持、進路選択、さらにはキャリア計画に至るまで、実体験に基づいた具体的なアドバイスを提供します。
単なる受験指導ではなく、「未来の自分をデザインする力」 を一緒に育てていきましょう。
まずは、お気軽にご相談ください。
ご連絡は以下のフォームからお待ちしております。
あなたの未来への第一歩を、ここから。